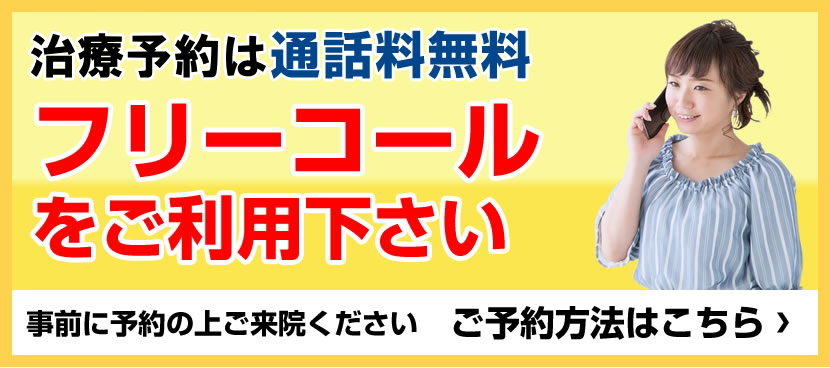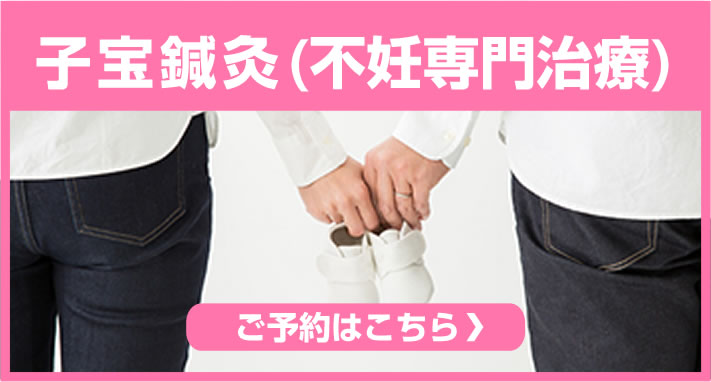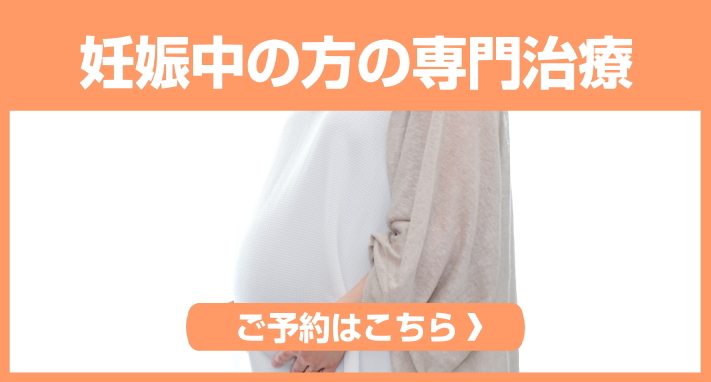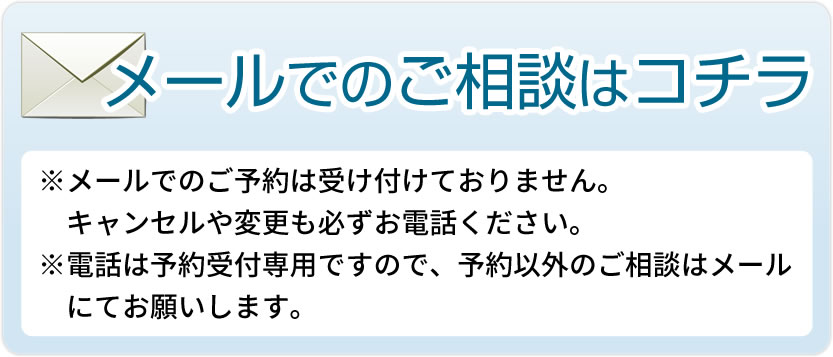外反母趾について
第60回研修会資料より
足はカラダの美容的・健康的問題を左右する重要な場所
足の形が崩れると、
・外反母趾 ・扁平足 ・O脚 ・変形性膝関節症 ・下半身太り ・股関節の変形 ・骨盤のゆがみ ・側彎症
など・・・
【外反母趾】
× 親指が外側に曲がっているもの
○ 『今日の整形外科治療指針』(医学書院)
「第一中足骨が内反、第一中足趾節関節で母趾基節関節骨が外反、中足骨骨頭が内側に膨隆し、『く』の字型の変形を起こしたもの」
↓↓↓
第一中足骨のねじれを伴うもの
原因
足は、カラダの中で一番負担がかかっている部位(重力に抗する基点)。
- 遺伝
第一中足骨が内反しやすい・骨質が弱い。 - 体重
体重が軽い方が多い。(正しい骨格を維持するのが難しい)
急に体重が増えた場合なりやすい。 - 運動不足
足の骨格を維持するのに十分な筋肉がない。 - 歩き方
ペタペタ歩くのはNG。(歩く時の音は歩行効率の悪さを表す)
足にかかる衝撃を分散させる歩き方が◎
→円運動(膝を使って歩く)
一本の腺を、踵の内側と親指で踏むようにし、つま先は真っ直ぐ。
足は膝から出す。(後ろ足は、地面を蹴るのではなく、膝を前に出す)
踵から着地する。 - 足に合わない靴と靴下
・先の細いハイヒール(締め付けすぎる)
ヒールは身長の1.5%だと良い。
ぺったんこな靴も負担大。
・靴下、ストッキング(つま先に弛みを作らずにはくと親指を外反状態にする)
長時間締め付けると良くないので、つま先は少し弛ませると良い。
・幅広の靴→開張足(横アーチの落ちたもの。足裏のタコやマメの原因) - 偏平足(足にかかる衝撃がうまく分散できない)
「舟状骨」が落ちることで起こる。
舟状骨とは、土踏まずの真上にある骨で、足の甲で“船底”のようなアーチを描く。
この骨が地面の方向に落ちるとアーチが崩れる。
<舟状骨を支える筋肉>
下から→長母趾屈筋と長趾屈筋
上に引き上げる→前脛骨筋と後脛骨筋
外反母趾を誘発する原因
重心が土踏まずの部分にかかるので、足の親指側への負担が増え、足底の親指の内側についている「母趾内転筋」が硬く縮み、加えて、幅の狭い、つま先が細くなった靴を履いている人は、親指が内側に圧迫されて「くの字」になりやすい。
すると足の甲から親指の付け根にかかる「第1中足骨」が内側に折れる。
この状態がひどくなると、本来は親指を外側に開く働きを持っているはずの「母趾外転筋」も骨と同時に小指側に入り込んでしまう。
すると、親指を開こうとしても言うことを聞かなくなる。
自分は、親指を開く方向に働かせているつもりなのに、母趾外転筋は反対に「内転」方向に働いて、親指を閉じるようになる。
結果的にどんどん外反母趾を増強してしまうため、外反母趾がひどい人は、足の親指を開く運動は注意して行う必要がある。
治療
- 手術
足の変形が強い・歩くだけで痛い・化膿している部分が治りにくい
軟部組織矯正術、中足骨骨切り術、基節骨骨切り術
関節破壊を認める症例には関節固定術や関節形成術・・・など。
入院期間4~5日。術後2週間は固定して安静に。 - テーピング・装具
意外と高額な上に、症状を悪化させることがある。
指の間に挟んで使用する装具は、中足靭帯を緩めて開張足を促してしまう。
ねじれの改善にならない。 - ストレッチ・運動
自分の足の状態に合わせたストレッチ・運動を組み合わせると◎
【ストレッチのコツ】
①リラックスしてやる。
②ゆっくり行う。
③弱めの力で行う。
↓↓↓
痛みや違和感は禁物。少し物足りないくらいが◎
【骨格のゆがみを取り除くには】
①ゆがみを解消する。
②インナーマッスルを鍛える。
③アウターマッスルを鍛える。
【いつ行うのが効果的??】
お風呂上がりや、お休み前
→ゆがみを解消したあとすぐに負担をかけないように。
このページは、千里堂治療院第60回研修会資料をもとに構成しました。
-参考-
山田光敏著『かんたんストレッチで外反母趾・巻き爪が治る本』PHP研究所/菊池和子著『奇跡のきくち体操 指の魔法』集英社/河野邦雄・伊藤隆造・堺章著『解剖学』盲学校理療科標準教科用図書/日経ヘルス&プルミエ『足裏の筋肉を鍛えて扁平足、外反母趾を解消 ゆがみリセット学11』
子宝鍼灸(不妊専門治療)・痔の専門治療・妊娠中の方のための専門治療は予約電話の番号が異なります。
地図・アクセス

お知らせ
更新情報
- 子宝治療で妊娠! 妊娠中の腰痛がつらくて来院。
- 頸椎ヘルニアによる肩・背・手指のシビレの治療
- 早期治療で痔の症状が良くなりました!
- 外痔と裂肛による痛みに対する鍼灸治療
- 肩こりや腰痛で定期的に通っています
経絡リンパセラピーのご紹介
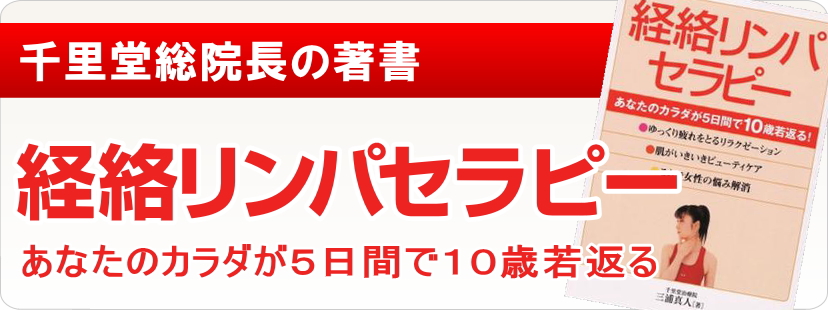
健康良品のご紹介《受療者様には優待販売もあります》